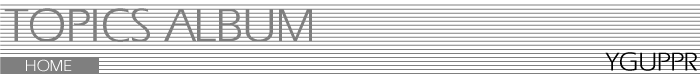
レポート『山梨のワイン』
|
山梨県は平成12年度都道府県別ワインの製成量(国税庁資料)において、ワインの製成量が全国1位となったのだ。山梨はワインの全国総製成量85,301キロリットル中、30,087キロリットル、シェアが35.3パーセントを占める。次点が製成量16,129キロリットル、シェアが18.9パーセントの神奈川県であり、優に約2倍の差がついている。 そして、このことより、山梨のワインを知ってもらうことは、日本のワイン産業の活性化につながるのではないだろうか。 まず、ワインとは、広い意味では果実から造る醸造酒のことをいうが、一般的には葡萄を原料とした酒を指すのである。 現在ではフランスはワインの一人当たりの消費量が世界12ヶ国中1位である(O.I.V資料)。フランスの、ワインの消費量は、世界合計22,379キロリットル中、3,550キロリットルである。一人当たりの消費量58.7リットルである。そして、僅差の2位でイタリアが入っている。イタリアは、消費量3,200キロリットル、一人当たり51.2リットルである。日本は、消費量320キロリットル、一人当たり2.5リットルである。この結果は、世界12ヶ国中、消費量及び一人当たりのワインの消費量が最下位であることを示す。尚、最下位からの次点として、消費量364キロリットル(一人当たり19.8リットル)のオーストラリアと、消費量2,080キロリットル(一人当たり7,9リットル)のアメリカである。このことからわかるように、日本はワインに対してあまり馴染みがない。 日本のワインの歴史は明治初期から始まり、日本でのワインの醸造は、西欧文化の移入と共に開始されたものといえる。生食用の葡萄からでもワインを造ることはできるが、水っぽくなり、酸味が足りない。生食用では、甘さが第1位である。しかし、醸造用(ワイン専用の葡萄)では、酸味はワインを造る上で、まろやかな味とコクを出す重要な要素といえる。また、ワインにするとき、葡萄は破砕するので、皮の厚さや粒の大きさなどの見た目の良さは必要ない。しかし、日本では、ワインの醸造は発展しなかったのである。理由としてあげられるのが、また、日本は気候的に水が豊かで、果物の汁を水代わりに飲む必要がないからである。それに、このとき、外国から様々な洋酒が入ってきたこともあり、日本は、醸造用の葡萄を作るのをやめたてしまった。これらのこともあり、日本の葡萄栽培は生食用に止まってしまい、醸造用に関心が向かなかったのである。次に、葡萄は、水(雨)に弱く、水はけのよい土地(盆地)ぐらいでしか育たない。それに、葡萄栽培は一時期に労力が集中するため家族労働では間に合わないのである。そのため、親族に手伝ってもらっている、というのが現状である。 だが、これらの問題点を解決しているのが、まず山梨の盆地(気候)である。山梨は戦国時代に、八珍果(8つの珍しい果物)が実るといわれていた。そのことから山梨は、果物が育つのに適した土地なのである。葡萄の樹は、暑すぎても寒すぎても育たない。樹の生育を抑制するだけの寒い夜や、成長を始めるのに適した穏やかな春や、また、開花と実の生育を促す十分な日照量のある暑い夏や、完熟させて豊かな香りをもたらす秋を必要とする。これらの四季が揃う場所(北緯30〜50度、南緯20〜40度の範囲)に、ワイン産地が集中している。主な産地として、フランス、イタリア、スペイン、日本、アメリカ、チリ、オーストラリアなどが挙げられる。そして、最も代表的な生産地がフランスである。フランスで造られるワインの品質は高く、世界のリーダー的存在である。 高級ワイン専用の葡萄栽培に適した気候は、フランスワインの本場である、ボルドー地方のような気候が最適といわれている。なぜなら、雨が少なく、昼と夜との温度差が大きいと、ミネラル豊富な葡萄果実ができるからである。そのボルドー地方と、白州の気候がよく似ているのである。比較的雨量が少ない内陸的気候であること。夏の最高気温は比較的に高めであるが、日中の最高気温のピークは短く、すぐに3度位低くなってくる。葡萄果実は8月中旬以降、ミネラルや糖分を蓄え始める。8月中旬を過ぎると急に秋風が吹き始め、夜は涼しくなり、昼と夜との温度差が大きく、この時の温度差が、高品質の葡萄を育てるのだ。また、醸造用に適した土壌は、水はけが良く、砂混じりの「やせた土地」であり、砂質土壌なのである。白州の土壌が正に砂質土壌であり、窒素が少なく、燐酸分が効きやすい、葡萄栽培には最も適した土壌環境となっているのである。また、山梨県北巨摩郡須玉町津金地区は標高800メートル、日照時間が多い割に夏が清涼であり、土壌の水はけが良い。これは、葡萄栽培に適してるうえ、過去13年間の気象データが銘醸地である、ボルドーとほぼ同じである。 また、自然の風土の他に、様々な取り組みも挙げることもできる。例えば、ヴォー・ペイサージュの代表者岡本英史さんは会員制の「葡萄倶楽部」を設立し、年数回、葡萄作りを手伝ってくれる人を募った。 また、山梨県は2003年4月10日に日本で第1号のワイン特区(ワイン産業振興特別区域、つまり特定地域に限って規制が緩和される)に認定されたのである。 今、現在、にわかにワイン業界がにぎわっている。そんな中で、山梨のワインは、日本人の味覚にマッチした健全で良質の信用に値するワインを造ろうと努力している。<参考文献> 1 ジョアナ・サイモン(小林令子訳)『ワインをもうちょっと知りたい』(株式会社阪急コミュニケーションズ、2003年8月)158頁 2 浅田勝美 『カラー版 日本のワイン』(角川書店、1977年9月) |