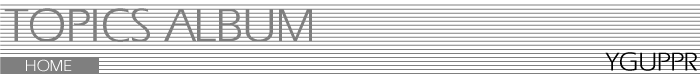
山梨学院創立60周年記念事業
「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」2日目
〜 国際会議 7ヶ国の研究者ら約100名がセッション 〜
「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」2日目
〜 国際会議 7ヶ国の研究者ら約100名がセッション 〜
 山梨学院大学(古屋忠彦学長)は10月7日、同大の山梨学院クリスタルタワーで、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」の国際会議を行った。ロシア、アメリカ、イギリス、中国、韓国、フィリピン、日本の7ヶ国の研究者ら約100名が出席して、開催セッション、第1セッション「日露戦争再考(1)」、第2セッション「日露戦争再考(2)」、第3セッション「戦争の記憶とロシア人」が行われた。 山梨学院大学(古屋忠彦学長)は10月7日、同大の山梨学院クリスタルタワーで、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」の国際会議を行った。ロシア、アメリカ、イギリス、中国、韓国、フィリピン、日本の7ヶ国の研究者ら約100名が出席して、開催セッション、第1セッション「日露戦争再考(1)」、第2セッション「日露戦争再考(2)」、第3セッション「戦争の記憶とロシア人」が行われた。開催セッションで古屋学長は「7カ国から多数の研究者をお招きし、昨日はオープニングセレモニー、平和友好植樹、記念碑除幕式、記念シンポジウムが行われました。今日、明日は、カンファレンスの一番重要な部分になろうかと思います。日露戦争から100年が経過した、この時期を捉えて新しい切り口で、ロシアと日本、そして関係諸国の友好のスタートが切れ、また、このカンファレンスを通じて、世界になんらかのメッセージ性をもてれば、主催大学としてそれに勝る喜びはありません。ご関係の研究者の皆様にエールを送り、併せて実り多い成果がもたらされますよう祈念いたします」と挨拶した。 我部政男プロジェクト代表は「第一回目から様々な面でご支援とご協力いただきました国際交流基金、政府、外務省始め関係機関の各位に対し、この場を借りて感謝と御礼を申し上げます。これからの2日間の国際会議が、日露戦争の多様な側面を深く掘り下げ、次の時代の国際交流、及び総合理解の指標となることを期待します」と述べた。 招聘者を代表してエフゲニー・コールチャギン氏が「2004年3月にサンクト・ペテルブルグで行われた第1回国際会議のテーマ『ポーツマス講和百周年』を継続して、今回はさらなる大事な話し合いや討議ができると思っております。また、テーマを継続し拡大していくことによって、参加各国の関係をより深めることができると思っています」と挨拶した。 セッションはサンクト・ペテルブルグでの会議を踏まえ、第1セッションは、コンスタンチン・サルキソフ氏のコーディネートで、テーマ「日露戦争再考(1)」について、アンドレイ・サハロフ氏「ロシアにおける日露戦争に対する新しいとらえ方」、中井晶夫氏「ドイツからみた日露戦争」、リカルド・ホセ氏「日露戦争が東南アジアに与えた影響」が発表された。 第2セッションは和田春樹氏のコーディネートでテーマ「日露戦争再考(2)」について、湯重南氏「日露戦争と中国」、イアン・ニッシュ氏「日露戦争後の中国」、金栄作氏「日露戦争と韓国」が発表された。 第3セッションは平間洋一氏のコーディネートでテーマ「戦争の記憶とロシア人」について、エフゲニー・コールチャギン氏「ロシア海軍中央博物館に保存されている日露戦争関係の貴重資料の考察」、セルゲイ・チェルニャフスキー氏「ロシア国民の記憶にのこる日露戦争」が発表された。 明日は、国際会議の第4・第5・第6セッションとラウンドテーブル・セッションが行われる予定となっている。 開催セッションアルバム 第1セッションアルバム 第2セッションアルバム 第3セッションアルバム |