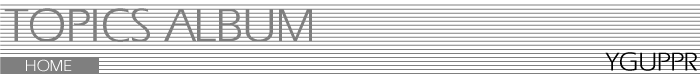
山梨学院創立60周年記念事業
「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」国際会議で閉幕
〜 日露戦争100年を契機に、東アジアの諸問題解決の研究を 〜
「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」国際会議で閉幕
〜 日露戦争100年を契機に、東アジアの諸問題解決の研究を 〜
 山梨学院大学(古屋忠彦学長)は10月8日、同大の山梨学院クリスタルタワーで、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」の国際会議を行った。この国際会議は、昨日からロシア、アメリカ、イギリス、中国、韓国、フィリピン、日本の7ヶ国の研究者ら約100名が出席して行われている。最終日の今日は、第4セッション「ポーツマス講和と東アジア(1)」、第5セッション「ポーツマス講和と東アジア(2)」、第6セッション「日露戦争再考(3)」、ラウンドテーブル・セッションが行われた。10月6日に開幕し、日露戦争の両国遺族や7ヶ国の研究者や学生らによる平和友好植樹・記念碑除幕式、記念シンポジウム、歓迎レセプション、日露戦争写真展など3日間に渡り行われた、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」も、国際会議終了と同時に閉幕した。 山梨学院大学(古屋忠彦学長)は10月8日、同大の山梨学院クリスタルタワーで、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」の国際会議を行った。この国際会議は、昨日からロシア、アメリカ、イギリス、中国、韓国、フィリピン、日本の7ヶ国の研究者ら約100名が出席して行われている。最終日の今日は、第4セッション「ポーツマス講和と東アジア(1)」、第5セッション「ポーツマス講和と東アジア(2)」、第6セッション「日露戦争再考(3)」、ラウンドテーブル・セッションが行われた。10月6日に開幕し、日露戦争の両国遺族や7ヶ国の研究者や学生らによる平和友好植樹・記念碑除幕式、記念シンポジウム、歓迎レセプション、日露戦争写真展など3日間に渡り行われた、「インターナショナル・カンファレンスinサカオリ『ポーツマス講和と東アジア』」も、国際会議終了と同時に閉幕した。昨日の第1セッションから第3セッションを継続して再開された第4セッションは、下斗米伸夫氏のコーディネートで、テーマ「ポーツマス講和と東アジア(1)」について、ニコライ・ワシリエフ氏「ポーツマス講和」、フィリップ・トウル氏「ポーツマス条約・ナショナリズム・世論」、エリザベス・ターロウ氏「ポーツマス講和とアメリカ」、コンスタンチン・サルキソフ氏「日露戦争から戦略的同盟まで‐ロシア公文書館の資料を中心に‐」が発表された。 第5セッションは、熊達雲氏のコーディネートで、テーマ「ポーツマス講和と東アジア(2)」について、ミハイル・メーア氏「ポーツマス講和後の中近東」、飯倉章氏「人種戦争としての日露戦争」、松本武彦氏「在日華僑からみた日露戦争」が発表された。 第6セッションは、黒澤文貴氏のコーディネートで、テーマ「日露戦争再考(3)」について、セルゲイ・クリモフスキー氏「1904‐1905年日露戦争中のロシアにおける海軍強化への社会運動」、マリーナ・マレヴィンスカヤ氏「ロシア海兵の日記・手紙に反映されている日露戦争‐公文書館の資料に基づいて‐」、河合利修氏「赤十字資料からみた日露戦争の捕虜救護」が発表された。 小菅信子氏のコーディネートで行われた、ラウンドテーブル・セッションでは、「日本における日露戦争は、文明国としてのアピールの戦争であった」「文明的、文化的戦争であったかどうかは、日露両国だけでなく、戦争に巻き込まれた諸外国をも入れて、総合的に結論を出すべきである」「中国で被害を受けた地域では、野蛮な戦争を行った日本とロシアに対して、100年経った今でも、強い違和感や反発がある。」「一番被害を受けたのは中国であり韓国である。日露両国は和解ができたといいながら、巻き込まれた国々の傷を癒すことができていない部分がある。」「日露戦争は、国際法を遵守した、文明を意識した戦争であったと申し上げたわけですが、基本的には文明対野蛮という見方がある文明です。日本が意識している文明とは、西洋に対しての、その姿を見せるということでありました。中国や韓国・朝鮮などは、あまり意識していない、そこに重要な問題が残っていいます。日本にとっては、未解決な部分として残っています。それが日露戦争100年を契機に、改めて日本の研究者にも突きつけられている問題だと思っております」「歴史的情報や資料を読み取るには、その当時の当該人物の立場で、その当時の新聞記事を読み、世論を見、世界情勢を見て、どうだなということを見ていただきたい。そうすることによって、資料と言うものは生きてくる」など、尽きることの無い様々な活発な意見交換が行われた。 コーディネートを務めた小菅氏は「この国際会議は、一つの切っ掛けで終点ではないと考えています。この会議で発表されたことや討論されたことは、論文集にまとめて来春には出版した意と考えています。この会議が、改めて開催されることを期待いたします。さらに、次のステップ、次の深み、深い洞察に入っていけたらと思います」と述べた。 我部政男プロジェクト代表は「この国際会議で、様々な意見が出されて、日露戦争というものが、国際的にもっていた様々な側面が照らし出された。2日間の国際会議が、日露戦争の多様な側面を深く掘り下げ、次の時代の国際交流及び総合理解の指標となることができたことを、発表された研究者や、参加された先生方に感謝すると共に敬意を表したい」と結んだ。 第4セッションアルバム 第5セッションアルバム 第6セッションアルバム ラウンドテーブル・セッションアルバム |