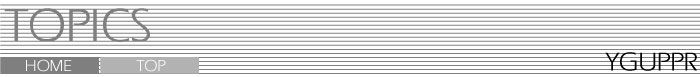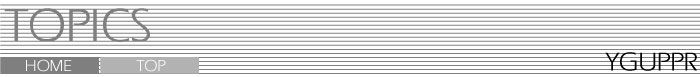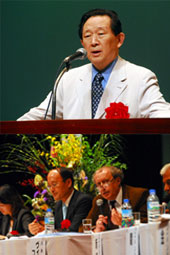 山梨学院生涯学習センター(共催:NPO法人山梨水と森の会、山梨日日新聞社、山梨放送、エフエム甲府)は7月8日、甲府市の山梨学院メモリアルホールで山梨学院創立60周年記念事業「環日本海生涯学習フォーラム」記念講演とパネルディスカッションを行った。詩人・作家の辻井喬(本名 堤清二 財団法人セゾン文化財団理事長)氏は、記念講演「東北アジア共同体は可能か?」について、「相手の文化や立場や真意などを、正確に理解し熟知したうえで、東北アジア共同体は可能か?について考えなければならない。歴史に鑑みて、罪などの歴史認識をはっきり持っている必要がある。日本は被爆国で、平和を基調とする国であり、平和憲法を貫き通す国であるとしなければならない。平和問題は、生活問題である。経済共同体ではなく、経済共同市場という考え方が必要で、独自性を主張しなければならない。既にポテンシャルは高まっている。これからのリーダーは、相手の立場に立ち、敵を味方に変える能力が不可欠で、覚えることは得意だが応用問題は不得意では困る。これからの時代は、受け取る能力と発信する能力が必要で、大学はこうした能力を身につけさせることが急務」と語った。 山梨学院生涯学習センター(共催:NPO法人山梨水と森の会、山梨日日新聞社、山梨放送、エフエム甲府)は7月8日、甲府市の山梨学院メモリアルホールで山梨学院創立60周年記念事業「環日本海生涯学習フォーラム」記念講演とパネルディスカッションを行った。詩人・作家の辻井喬(本名 堤清二 財団法人セゾン文化財団理事長)氏は、記念講演「東北アジア共同体は可能か?」について、「相手の文化や立場や真意などを、正確に理解し熟知したうえで、東北アジア共同体は可能か?について考えなければならない。歴史に鑑みて、罪などの歴史認識をはっきり持っている必要がある。日本は被爆国で、平和を基調とする国であり、平和憲法を貫き通す国であるとしなければならない。平和問題は、生活問題である。経済共同体ではなく、経済共同市場という考え方が必要で、独自性を主張しなければならない。既にポテンシャルは高まっている。これからのリーダーは、相手の立場に立ち、敵を味方に変える能力が不可欠で、覚えることは得意だが応用問題は不得意では困る。これからの時代は、受け取る能力と発信する能力が必要で、大学はこうした能力を身につけさせることが急務」と語った。
パネルディスカッション「平和と文化の地域拠点としての大学の役割をめぐって」は、パネリストの高益民(北京師範大学国際比較教育研究所副所長)氏は「地域・社会に向けつつある中国の大学〜市場化改革下における大学の役割転換〜」、丁妍(上海復旦大学高等教育研究所講師)氏は「地域社会に対する大学の貢献〜復旦大学の事例から〜」、呉在一(全南大学校行政学科教授)氏は「平和と文化の地域拠点としての大学の役割 A Korean Viewpoint」、ヴィクトル・コルスノフ(サハリン国立総合大学副学長)氏は「サハリン州の持続的発展と『地域大学』の役割」について発表した。
コメンテーターの新保敦子(早稲田大学教授)氏は「中国の大学は、市場化による大学の地域性の強化や資金調達に追われ、沿海部と内陸部、都市と農村の地域格差が拡大している。今後に向けて、若い世代が『地球市民』として育成していくことが必要だということがわかった。これは日本の大学にもいえることだ」と述べた。関啓子(一橋大学教授)氏は「サハリン国立大学にみられる地域の特徴を活かした教育は素晴らしい。少数民族への教育的配慮や市民などへのきめ細かな生涯学習、補完教育。また、サハリンは豊かな自然に恵まれたところ、その自然を守るためにエコロジーに取り組んでいる素晴らしい。環境問題は地球規模の問題」と述べた。金雲鎬(山梨学院大学専任講師)氏は「東北アジアにおける平和を脅かす潜在的なことを、マクロとミクロ、ミクロとマクロという話でよく理解できた。国と国では摩擦があるが、市民レベルでは何の問題もない。大学は隣国と共に生きる教育プログラムを具体的に推進することが必要だ」と述べた。
コーディネーターの小菅信子(山梨学院大学教授)氏は「①大学の地域社会に対する貢献の期待が高まっている。②一方で、大学の抱える問題も多くあるが、様々な有意義な試行錯誤がされている。③大学は、東北アジアの平和と共生のために、偏見や固定概念を取り払うなどの、相互理解を深める拠点となる努力をしなければならない。④大学は、地域が必要とする教育をめぐるコンセプトづくりと、その活用を行うべきだ。たとえば補足教育や生涯学習など、ニーズにあった教育への取り組みが必要となる。⑤大学は地域の資源を活用するとともに環境保全に努めるべきなど、有意義な討論ができた」とまとめた。
椎名愼太郎(山梨学院大学大学院教授)氏は「中国・韓国・ロシア・日本と四つの地域のパネリストが、東北アジアの平和について話し合いができたことは素晴らしいことだ。大学が、この地域の平和についての相互理解を果たす役割が必要、今回のパネルディスカッションが出発点となったことの意義は大きい」と結んだ。
アルバム|フォーラム|記念講演|パネルディスカッション|
|