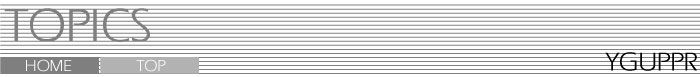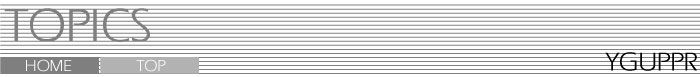山梨学院大学 (法学部政治行政学科・行政研究センター)は7月19日、甲府市の山梨学院メモリアルホールで、財団法人東京市政調査会理事長・東京大学名誉教授の西尾勝氏を講師に招き、山梨学院創立60周年記念講演会「分権改革と政治改革」を行った。 山梨学院大学 (法学部政治行政学科・行政研究センター)は7月19日、甲府市の山梨学院メモリアルホールで、財団法人東京市政調査会理事長・東京大学名誉教授の西尾勝氏を講師に招き、山梨学院創立60周年記念講演会「分権改革と政治改革」を行った。
西尾氏は、1995年から2001年まで、地方分権推進委員会委員。2000年から21世紀臨調「新しい日本をつくる国民会議」に参画。この自分史を語り、Ⅰ.分権改革は行政改革の流れと政治改革の流れの合流点で生まれたとして、(1)1980年代以来の行政改革と1990年代以来の政治改革の流れ(選挙制度改革等。政治家による地元利益の仲介斡旋の改革。政界再編成)。(2)分権改革の起点は、①1993年の衆参両院の地方分権推進決議と第3次行革審の最終答申、②1994年の村山内閣の下で地方分権推進大綱の閣議決定、③1995年の地方分権推進法の制定と地方分権推進委員会の発足をあげ、(3)分権改革の「政策の窓」を開いた二つの要因は①地方分権を要求する政治勢力の多元化(地方自治業界 政界・財界・労働界)、②自民党一党単独支配時代から連立政権時代への移行、(4)村山内閣による地方分権推進委員会の人選を挙げた。
次に、Ⅱ.地方分権推進委員会の基本戦略について、(1)地方六団体の支援を背景に、国の各省庁と折衝、①地方六団体が反対するような改革はしない(「受け皿」議論の棚上げ)。②地方六団体に改革要望の提出を要請。(2)予定外の中途での戦略変更(市町村合併の同時進行にゴーサイン)、(3)内閣の勧告尊重義務はどのように働いたか。1996年3月の中間報告に各省庁は反発。橋本首相は「現実的で、実行可能な勧告を望む」と繰り返し述べた。閣議決定可能な勧告、全省庁が同意している勧告である。そこで、その後の勧告に向けた作業では「霞が関ルール」を尊重した。つまり、関係省庁が同意した事項のみを勧告したと語った。
Ⅲ.戦後日本の議院内閣制における閣議決定の仕組みについて、(1)省庁間折衝による全省庁の合意の形成、(2)政府与党間折衝、(3)事務次官等会議、閣議決定、法案等の国会提出、(4)各省庁は拒否権を保有していると紹介。
Ⅳ.地方分権推進委員会の最終局面での大きな二つの挫折について、(1)第5次勧告の挫折(公共事業の国直轄事業の一部を都道府県に移管する試みの挫折)。(2)国庫補助負担金の大幅縮小と国税から地方税への税源移譲(大蔵省<財務省>の頑強な反対で勧告にできず、提言に止める)。(3)この二つの挫折の体験から、21世紀臨調への参画を決意する。(4)最終報告、片山ブラン、「三位一体の改革」①国から地方への補助金の削減、②国税から地方税への税源移譲、③地方交付税制度の見直し、の3つを掲げた。
Ⅴ.その後の政治改革の流れについて、(1)橋本行革、①内閣機能の強化、②中央省庁の再編成、③独立行政法人制度の創設(国立大学法人制度の創設)、④政策評価制度の導入、(2)小沢構想(イギリスの議院内閣制構想)、①副大臣・大臣政務官制度の導入、②政府委員制度の導入、③党首討論制度の導入、(3)最も重要なのは、橋本行革による内閣機能の強化、①首相の閣議への基本方針の発議権、②経済財政運営の基本方針を策定する経済財政諮問会議の創設。(4)この橋本行革の成果を始めて活用したのが小泉内閣、①経済財政運営及び構造改革に関する基本方針(骨太の方針)、②経済財政諮問会議の策定、閣議決定、事務次官等会議のバイパス、③自民党内に「抵抗勢力」が誕生、自民党総務会のバイパス、④道路公団等民営化や郵政事業民営化はこのバイパスの成果。(5)分権改革も未完、政治改革も未完、と述べた。
Ⅵ.「三位一体の改革」は第2次分権改革、第3次分権改革の要は「道州制」とし、道州制とは何かは誰にも答えられない。いかなる道州制がよいかを議論することが最も重要な問題。「道州制」は分権改革を更に促進する方策にもなり得る反面、分権改革を後退させる方策にもなり得る。その意味で、迂闊に乗れない危険性が伴う代物である。そこで、当面は都道府県間の合併や統合などの再編成といった着実な歩みを進めた方が無難だと考えていると述べた。
おわりに会場を埋め尽くした約600名の聴衆に、分権改革を更に促進するためには、各省庁官僚機構の頑強な抵抗に直面しても、内閣の意思を貫徹し切るような、小泉内閣よりも更に強力な指導力をもった内閣の誕生が不可欠とし、分権改革を進めるには政治改革が必要で、これは表裏一体のものだと説いた。
アルバムはこちら |