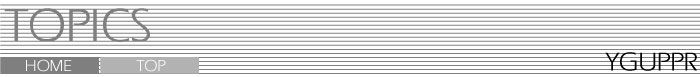
大賞・文部科学大臣奨励賞 島津あいりさん(中3)
~ 応募数38395句 年齢 最高96歳・最低4歳 ~
第八回酒折連歌賞は、①「踏んでゆくふるさとといふ土はどこまで」、②「スニーカー履いて明日は変身をする」、③「うたたねの夢さめて聴く夜の雨音」、④「雨あがるこころの虹がゆらめきながら」の片歌の中から①から④句を選び、『5・7・7』の答えの片歌を作って応募してもらう。応募期間は、平成18年4月1日(土)から9月30日(土)消印有効で、国内や海外から38395句が寄せられた。 【大 賞】 【評】虹のはじまりと虹のおわり。作者の中にある「こころの虹」がどこかへの思いへとつながってゆく一瞬が託されています。読み終えた後に虹はなにか人のこころの中にある思いのようなものをつないでいるということを教えてくれる作品です。虹は夜空へとつながりながらそのつながりはまっすぐではなくて、進んだり躊躇ったりしたこころの形にも似た「らせん階段」で表現されているところに心情がとてもよく現われています。「こころの虹」の描くアーチと「らせん階段」の曲線がうまくとけあった視覚的にも面白い片歌です。 (もりまりこ) 【佳 作】 【評】問いの片歌を受けてなかなかの発想です。作者が高校三年、十七歳と聞きますとその〝ふるさと〟に向けられた心情の表裏に思わす納得するものがありました。この年令になれば、おそらくふるさとへの意識には相反する二つのものの相克が生まれてくるのでしょう。また今日もまた今日もと繰返しながら過ぎてゆく時の流れの中で生きているのが人間という存在です。世代を代表する表現として推奨します。(廣瀬直人) 【佳 作】 【評】離れればこそ「ふるさと」は生まれ、「ふるさと」の持つ意味がわかるものです。帰ってきたふるさとの土の道を歩いているとき、傍らに見つけた「さぎ草」。それはかつてふるさとから旅立っていった兄弟や仲間たちを思い起こさせるように、「向きそれぞれに飛び立つ構え」をして咲いていました。「ふるさと」を離れる日の希望と不安とが、「さぎ草」の白く純真で繊細な花に重ね合わ 【佳 作】 【評】まず、「ぼくは樹だ」という断定の、思いがけない強さに惹きつけられました。それは「夢」のなかでの疑いのない感覚でしょう。「ぼく」の魂は樹に入り込み、空からのキス=雨に、枝葉をふるわせて歓喜したのです。そして、目を覚ますと、いつのまにか外は夜の雨になっていたのでした。人間と樹木の交感を描いて間然するところがありません。表現の強さが歓喜の感覚と結びつ 【アルテア賞最優秀賞】 【評】「こころの虹」のなかをゆっくりと舞ってゆく「てふてふ」。風の重力を纏いながらこちらまで舞ってきているそんな蝶々の浮遊感を、リズミカルに捉えています。「ひらがなで舞う」という発見が、「虹のゆらめき」と対話しているように、やわらかな意思と希望を静かに伝えてくれる、みずみずしい作品です。(もりまりこ) 【第八回酒折連歌賞100選】はこちら 選考委員の総評が問いの片歌ごとに発表された。 問いの片歌 ① 踏んでゆくふるさとといふ土はどこまで (廣瀬直人) 今年もまた沢山の応募作品に接することが出来ました。選を終えて自分なりの結論を出したあとは、さすがに疲労感が残りますが、あらためて選出した作品を読み直し、さらに声に出して口ずさんでいますと。少々ぼんやりしていた頭の中をひとすじの澄んだ川音が流れ過ぎていくように思えます。これは選者だけに与えられる醍醐味といっていいでしょう。 問いの片歌 ② スニーカー履いて明日は変身をする (三枝昂之) 私の問いは「スニーカー履いて明日は変身をする」でした。どんな人にも変身願望がありますね。石川啄木は明治四十三年に「うすみどり/飲めば身体【ルビからだ】が水のごと透きとほるてふ/薬はなきか」と詠って、透明人間願望を示しています。もちろん「なきか」ですから、そんな薬はないことを承知の上ではかなくも願っているのです。透明人間になる薬はあまりに非現実的ですから、ここでは履き物を替えたらどんな変身ができるだろうか、とそんな身近な設定の中でみなさんに問いかけてみたわけです。私たちにも変身願望はあります。帽子をかぶること、お化粧をすることも小さな変身です。 問いの片歌 ③ うたたねの夢さめて聴く夜の雨音 (深沢眞二) 第8回酒折連歌賞の選考を終えて、何よりも印象に残ったのは、中学・高校の団体応募作品のレベルの向上です。各校の先生方が、刊行されている第5回までの優秀作品集をお読みになり、この片歌問答に求められる言語コミュニケーションの妙味を理解したうえで、指導なさっていることがよくわかりました。感謝申し上げます。ただ、そのように過去の優秀作が応募者の目に触れやすくなったことで、俳句で言う「等類」が、意識されずとも生み出されやすくなったとも言えます。「等類」と「反転」の差は微妙です。作品の独創性を見逃さないように心がけて選考いたしました。 問いの片歌 ④ 雨あがるこころの虹がゆらめきながら (もりまりこ) 気がつくと、さっきまでずっと降り続けていた雨がすっかりやんでいて、空を見上げるとうっすらと虹が浮かんでる。こんな光景はいつでも見られるわけじゃないのに思いがけず出会ったことの一瞬のよろこびに満ちています。今回はそんな虹を片歌に託してみたくて作ってみました。雨上がりの空に見える虹ではなくて、こころの中に佇んでいる虹。こころの中にかかっているあなたの虹のかたちはどんな思いがつまっていますかという問いかけに、たくさんの答えの片歌と出会うことができました。 |
 第八回酒折連歌賞実行委員会(川手千興委員長)は1月31日、第八回酒折連歌賞100選を発表した。応募数38395句の中から、大賞・文部科学大臣奨励賞には、中学3年生の島津あいりさん(14歳・愛知県)の作品が、佳作には、仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、平井玲子さん(73歳・山梨県)、大原薫さん(32歳・神奈川県)が、アルテア賞最優秀には、前田三菜津さん(17歳・京都府)が選ばれた。大賞の島津あいりさんは、問いの片歌「雨あがるこころの虹がゆらめきながら」に「夜空へとつながってゆくらせん階段」と答えの片歌を詠んだ。選考委員は「作者の中にある『こころの虹』がどこかへの思いへとつながってゆく一瞬が託されている。虹は夜空へとつながりながらそのつながりはまっすぐではなくて、進んだり躊躇ったりしたこころの形にも似た『らせん階段』で表現されているところに心情がとてもよく現われている。『こころの虹』の描くアーチと『らせん階段』の曲線がうまくとけあった視覚的にも面白い片歌」と絶賛した。なお、最高年齢は96歳、最低年齢は4歳。海外からは487句が寄せられた。
第八回酒折連歌賞実行委員会(川手千興委員長)は1月31日、第八回酒折連歌賞100選を発表した。応募数38395句の中から、大賞・文部科学大臣奨励賞には、中学3年生の島津あいりさん(14歳・愛知県)の作品が、佳作には、仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、平井玲子さん(73歳・山梨県)、大原薫さん(32歳・神奈川県)が、アルテア賞最優秀には、前田三菜津さん(17歳・京都府)が選ばれた。大賞の島津あいりさんは、問いの片歌「雨あがるこころの虹がゆらめきながら」に「夜空へとつながってゆくらせん階段」と答えの片歌を詠んだ。選考委員は「作者の中にある『こころの虹』がどこかへの思いへとつながってゆく一瞬が託されている。虹は夜空へとつながりながらそのつながりはまっすぐではなくて、進んだり躊躇ったりしたこころの形にも似た『らせん階段』で表現されているところに心情がとてもよく現われている。『こころの虹』の描くアーチと『らせん階段』の曲線がうまくとけあった視覚的にも面白い片歌」と絶賛した。なお、最高年齢は96歳、最低年齢は4歳。海外からは487句が寄せられた。