 山梨学院大学(古屋忠彦学長)と酒折連歌賞実行委員会(川手千興実行委員長)は2月26日、山梨学院大学広報スタジオで「五・七・七」の問いの片歌に、「五・七・七」の答えの片歌を詠む第八回酒折連歌賞(文部科学省後援など)の表彰式を行った。主催者代表の古屋学長は、大賞の島津あいりさん(14歳・愛知県)、佳作の平井玲子さん(73歳・山梨県)、アルテア賞最優秀の前田三菜津さん(17歳・京都府)に、代理人出席となった佳作の仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、大原薫さん(32歳・神奈川県)に、賞状や副賞をそれぞれ授与し応募数38395句の五傑の栄誉を称えた。大賞の島津さんには文部科学大臣奨励賞も手渡された。 山梨学院大学(古屋忠彦学長)と酒折連歌賞実行委員会(川手千興実行委員長)は2月26日、山梨学院大学広報スタジオで「五・七・七」の問いの片歌に、「五・七・七」の答えの片歌を詠む第八回酒折連歌賞(文部科学省後援など)の表彰式を行った。主催者代表の古屋学長は、大賞の島津あいりさん(14歳・愛知県)、佳作の平井玲子さん(73歳・山梨県)、アルテア賞最優秀の前田三菜津さん(17歳・京都府)に、代理人出席となった佳作の仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、大原薫さん(32歳・神奈川県)に、賞状や副賞をそれぞれ授与し応募数38395句の五傑の栄誉を称えた。大賞の島津さんには文部科学大臣奨励賞も手渡された。
川手実行委員長は「言の葉連ねて歌遊び『五・七・七』の問いの片歌に、『五・七・七』の答えの片歌を詠む酒折連歌賞に、4年連続となる3万句を超える作品が寄せられた。その中から今日、お越しの5名が選ばれました」と挨拶。廣瀬直人選考委員長は「八回を数えて『五・七・七』が皆さんに定着してきた。受賞者は、日常の体験の中から引き出したものを自分の言葉で表現している」と述べた。三枝昂之選考委員、深沢眞二選考委員、もりまりこ選考委員は「今回も、問いの片歌に、想像を絶する答えの片歌が寄せられた。ここにお越しの受賞者は、それを含めて答えの片歌が秀でていた。酒折連歌は、問いの片歌に、答えの片歌を詠むコミュニケーションの古くからある日本文学の原点。現在、携帯メールでコミュニケーションをとり、また歌を詠む時代となった。日本語ブームに後押しをされ酒折連歌賞も3万句を超える文学賞となった。今、流行の脳トレにもなるので、これからも創作してもらいたい」と述べた。
大賞の島津あいり(愛知県)さんは、問いの片歌『雨あがるこころの虹がゆらめきながら』に、答えの片歌『夜空へとつながってゆくらせん階段』と詠んだ。島津さんは「現在は、いじめとかで自殺する若者が増えています。悩んだとき自殺をするのでなくて勇気を持って一歩踏み出してほしい。最初は暗くてはっきり見えないらせん階段は紆余曲折があると思いますが、やがて夜空へとつながり、その先は心の悩みが晴れ、希望の光が見えるはず、という思いを詠みました。まさか大賞をもらえるとは思わなかったのでビックリしています」と受賞を無邪気に喜んだ。
佳作の平井玲子(山梨県)さんは、問いの片歌『踏んでゆくふるさとといふ土はどこまで』に、答えの片歌『さぎ草の向きそれぞれに飛び立つ構え』と詠った。平井さんは「毎年、趣味で育てている鷺草、今頃芽が出てきて初夏には花をつけます。息子3人を同じ環境で同じように愛情を持って育てても、独立してそれぞれまったく違った道に旅立ちました。ただ鷺と違ってふるさとを巣立った息子3人は、ふるさとの土を思い出してお盆と正月には家族を連れて戻ってきます。こんな情景を重ねた句がある日、自然に飛んできました。酒折連歌を山梨文化学園の講座で2年間学び応募しましたが落選し、受賞を諦めていただけに嬉しい」と受賞を手放しで喜んでいた。
アルテア賞最優秀の前田三菜津(京都府)さんは、問いの片歌『雨あがるこころの虹がゆらめきながら』に、答えの片歌『光浴びてふてふと舞うひらがなで舞う』と詠んだ。前田さんは「学校の授業で課題として取り組んで、古文の勉強で『てふてふ』という言葉を見たときに、日本独特の古文とひらがなで華麗に舞い上がる蝶を思い浮かべながら作りました。『五・七・七』で作るのは初めてだったので大変新鮮に感じました」と受賞の喜びをじっくりと噛み締めていた。
表彰式の後、受賞者らは甲府市内にある連歌の発祥の地「酒折宮」を訪れた。
アルバムはこちら |
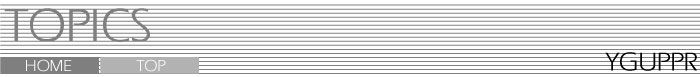
 山梨学院大学(古屋忠彦学長)と酒折連歌賞実行委員会(川手千興実行委員長)は2月26日、山梨学院大学広報スタジオで「五・七・七」の問いの片歌に、「五・七・七」の答えの片歌を詠む第八回酒折連歌賞(文部科学省後援など)の表彰式を行った。主催者代表の古屋学長は、大賞の島津あいりさん(14歳・愛知県)、佳作の平井玲子さん(73歳・山梨県)、アルテア賞最優秀の前田三菜津さん(17歳・京都府)に、代理人出席となった佳作の仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、大原薫さん(32歳・神奈川県)に、賞状や副賞をそれぞれ授与し応募数38395句の五傑の栄誉を称えた。大賞の島津さんには文部科学大臣奨励賞も手渡された。
山梨学院大学(古屋忠彦学長)と酒折連歌賞実行委員会(川手千興実行委員長)は2月26日、山梨学院大学広報スタジオで「五・七・七」の問いの片歌に、「五・七・七」の答えの片歌を詠む第八回酒折連歌賞(文部科学省後援など)の表彰式を行った。主催者代表の古屋学長は、大賞の島津あいりさん(14歳・愛知県)、佳作の平井玲子さん(73歳・山梨県)、アルテア賞最優秀の前田三菜津さん(17歳・京都府)に、代理人出席となった佳作の仁平井麻衣さん(17歳・東京都)、大原薫さん(32歳・神奈川県)に、賞状や副賞をそれぞれ授与し応募数38395句の五傑の栄誉を称えた。大賞の島津さんには文部科学大臣奨励賞も手渡された。