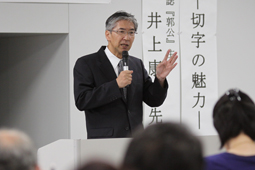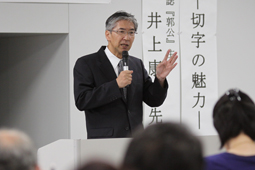
山梨学院生涯学習センターは7月12日、酒折連歌講座2014の第3回講座を開催した。この講座は山梨学院大学と酒折連歌賞実行委員会が主催する「酒折連歌賞」の10周年を記念して始まり、今年で7年目を迎える。今年度は全3回の講座が企画され、第1回目は5月10日に、歌人で酒折連歌賞選考委員を務める今野寿美さんが「今の心で片歌問答」と題し行われ、第2回目は6月14日に酒折連歌賞実行委員会の川手千興委員長が「酒折連歌における問いの片歌」について講座を行った。第3回目は今年から酒折連歌賞の選考委員を務めている俳人の井上康明さんが担当。受講した市民約70人を前に「俳句−切れ字の魅力−」をテーマに講座を行い、酒折連歌の作歌のポイントについて俳句の切れ字を参考に「俳句は切れ字があることで、裏切りや驚きがあり、酒折連歌においても問いの謎、疑問からくる常識的な反応をいかに裏切り、自分の心の中で新たな人生の物語を紡ぎ、人生的な情景の深さの中で詠んで答えるかがポイントとなる」と語った。
酒折連歌講座は、山梨学院大と酒折連歌賞実行委員会が主催する「酒折連歌賞」が創設10周年を迎えた2008年に記念事業として実施され、その後も山梨県内への「酒折連歌」の普及・啓発、文学の振興、文化の創造に寄与するため毎年開講し、今年で7年目を迎える。今年度の講座は全3回予定され、第1回目は5月10日に、歌人で酒折連歌賞選考委員の今野寿美さんが担当し、第2回目は酒折連歌賞実行委員会の川手千興委員長が担当。第1回目は「今の心で片歌問答」、第2回目は「酒折連歌における問いの片歌」をテーマにそれぞれ行われた。第3回目は、今年から酒折連歌賞の選考委員を務める俳人の井上康明さんが担当した。
講師の井上康明さんは1952年生まれ。俳人。俳誌『郭公』主宰。句集に『四方』『峡谷』。著作に『山梨の文学』(共著)など。山梨県の県立高校国語科教諭を経て山梨県立文学館に勤務(2012年退職)。二十代で俳句を始め飯田龍太、廣瀬直人に師事。「雲母」会員、「白露」同人を経て現在に至る。山梨日日新聞俳句欄選者。NHK全国俳句大会選考委員。
会場となった生涯学習センター講義室には、国文学や短詩型文学などに興味がある市民約70人が詰め掛け、井上さんの話に耳を傾けた。講座は「俳句−切れ字の魅力−」と題し進められ、井上さんは「俳句において“切れ”とは、ことばとことば、フレーズを切ることであり、俳句に休止と間合いが生じ、豊かな味わいがもたらされる。“や”“かな”“けり”が代表的な切れ字です」と説明し、久保田万太郎や飯田蛇笏、芥川龍之介の句を用いながら、切れ字によって句に現れる魅力や面白さを解説した。また、過去の十一回から十五回までの酒折連歌賞の大賞作品を紹介し、それぞれの作品の問いの片歌と答えの片歌の関連性・つながりなどについて選評をもとに解説を加えた。その上で、俳句の切れ字を参考に作歌のポイントとして「酒折連歌の問いの片歌は一つの独立した歌であり、答えの片歌を作る人は自分の中に受け入れて、自分の心の中で、新たな人生の物語を紡いで、問いの片歌が発した問いに、常識的な答えから裏切る答えを出すことが必要。俳句は切れ字があることで、裏切りや驚きがあり、酒折連歌においても問いの謎、疑問からくる常識的な反応をいかに裏切り、人生的な情景の深さの中で詠んで答えるかがポイントとなる」と語った。
「酒折連歌賞」は今回で16回目を数え、“酒折連歌”は五・七・七の問いの片歌に、答えの片歌を五・七・七で返す二句一連の片歌問答。俳句などと違い、作歌上の約束事は五・七・七で返すことのみ。問いの片歌に続く答えの片歌を作者の感性で自由に発想し、老若男女を問わず詠むことができる歌遊び。今年の第十六回酒折連歌賞は6月1日から募集が開始され、今回から表彰を全応募作品を対象とした一般部門と小・中・高校生の作品を対象としたアルテア賞部門に分け、それぞれの大賞に文部科学大臣賞などが贈られる。応募の締め切りは9月30日必着。
詳しい募集内容と応募の問い合わせは
山梨学院大酒折連歌賞事務局(TEL055-224−1641 ホームページ)
文・カメラ(Y.Y)2014.7.12
アルバムはこちら