●文部科学大臣賞第二十二回酒折連歌賞発表
~一般部門大賞 荒井千代子さん 45,915句から選定~
~アルテア部門大賞 橋爪杏奈さん(蒲原中)が受賞~
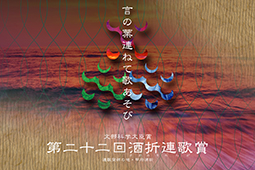 言の葉連ねて歌あそびの酒折連歌賞実行委員会(廣瀬孝嘉実行委員長)は2月1日、第二十二回酒折連歌賞の入賞100選の発表を行なった。この連歌賞は1998年に山梨学院大学が『連歌の発祥地』とされる甲府市酒折にちなんで創設。一般部門の大賞 文部科学大臣賞は荒井千代子さん(68歳 新潟県)が、問いの片歌「北斎の富士の角度は三十八度」に、答えの片歌「今もまだ測量してる伊能忠敬」と、答えの片歌を詠み45,915句の頂点に立つ大賞を受賞した。山梨県知事賞に武井大山さん(15歳 香川県 高松市立桜町中学校3年)が、山梨県教育委員会教育長賞に大沢美羽さん(18歳 山梨県立北杜高等学校3年)が、甲府市長賞に高橋亨さん(64歳 青森県)が輝いた。また、応募者の中から小・中・高校生対象のアルテア部門の大賞 文部科学大臣賞は橋爪杏奈さん(12歳 静岡県 静岡市立蒲原中学校)が、問いの片歌「はればれと一円玉は一グラムです」に、答えの片歌「恋の歌軽すぎるから心が揺れる」と、答えの片歌を詠み30,730句の中から受賞した。一般部門の大賞 荒井さんは「『北斎』『富士山』『角度』をキーワードに考えを巡らせ、ふと測量の父と呼ばれる江戸時代の人物『伊能忠敬』が浮かび、二百年も前に詳細な日本地図を作った。ご隠居の年齢だったはず。その熱い想いは彼の死後も燃え、今も測量を続けているのではと想像した。現在コロナウイルスが世界中に禍を招いている。外出や人との交流もままならず、閉塞感が社会を覆っている。外出は出来なくとも想像で無限の世界に行ける。この時代にこのような楽しみを持っていて良かったと思う」と述べた。入賞100選は『酒折連歌賞ホームページ』に掲載されている。
言の葉連ねて歌あそびの酒折連歌賞実行委員会(廣瀬孝嘉実行委員長)は2月1日、第二十二回酒折連歌賞の入賞100選の発表を行なった。この連歌賞は1998年に山梨学院大学が『連歌の発祥地』とされる甲府市酒折にちなんで創設。一般部門の大賞 文部科学大臣賞は荒井千代子さん(68歳 新潟県)が、問いの片歌「北斎の富士の角度は三十八度」に、答えの片歌「今もまだ測量してる伊能忠敬」と、答えの片歌を詠み45,915句の頂点に立つ大賞を受賞した。山梨県知事賞に武井大山さん(15歳 香川県 高松市立桜町中学校3年)が、山梨県教育委員会教育長賞に大沢美羽さん(18歳 山梨県立北杜高等学校3年)が、甲府市長賞に高橋亨さん(64歳 青森県)が輝いた。また、応募者の中から小・中・高校生対象のアルテア部門の大賞 文部科学大臣賞は橋爪杏奈さん(12歳 静岡県 静岡市立蒲原中学校)が、問いの片歌「はればれと一円玉は一グラムです」に、答えの片歌「恋の歌軽すぎるから心が揺れる」と、答えの片歌を詠み30,730句の中から受賞した。一般部門の大賞 荒井さんは「『北斎』『富士山』『角度』をキーワードに考えを巡らせ、ふと測量の父と呼ばれる江戸時代の人物『伊能忠敬』が浮かび、二百年も前に詳細な日本地図を作った。ご隠居の年齢だったはず。その熱い想いは彼の死後も燃え、今も測量を続けているのではと想像した。現在コロナウイルスが世界中に禍を招いている。外出や人との交流もままならず、閉塞感が社会を覆っている。外出は出来なくとも想像で無限の世界に行ける。この時代にこのような楽しみを持っていて良かったと思う」と述べた。入賞100選は『酒折連歌賞ホームページ』に掲載されている。
◾️第二十二回酒折連歌賞概要◾️
▷山梨学院大学は、山梨県甲府市の酒折宮でヤマトタケルノミコトと火焚きの老人が片歌問答で歌を詠んだ(『古事記』『日本書紀』)、このことから酒折宮が連歌の発祥の地とされ、これにちなみ問いの片歌五・七・七に、答えの片歌五・七・七を重ねる歌あそびを1998年創設。
▷二十二回を数える今回は、応募期間は2020年4月1日(水)から2020年9月30日(水)までの6か月。問いの片歌は、一「はればれと一円玉は一グラムです」、二「親ゆびと小ゆびひろげて距離をはかって」、三「歩く意志なくても進む朝の雑踏」、四「これだけは手放さないよあきらめないよ」、五「北斎の富士の角度は三十八度」の五句。これらの問いの片歌一~五の中から一句を選び、答えの片歌を五・七・七でつくって応募してもらった。なお、提示された問いの片歌五句すべて、また、応募句数にも制限なしで募集した。
▷選考は宇多喜代子(俳人)・三枝昻之(歌人)・今野寿美(歌人)・井上康明(俳人)・もりまりこ(歌人)の5人の選考委員が10月の上旬から選考を開始し、2021年2月1日に『酒折連歌賞ホームページ』などで公表となった。
◾️一般部門受賞者◾️
●大賞 文部科学大臣賞 荒井千代子さん(68歳 新潟県)
【問いの片歌】 北斎の富士の角度は三十八度
【答えの片歌】 今もまだ測量してる伊能忠敬
《 選 評 》
▶︎井上康明(いのうえ やすあき)先生
問いの片歌は、江戸時代に遡り、葛飾北斎が、富士山の姿を鋭く捉えた一瞬を示します。北斎の浮世絵、「凱風快晴」に描かれた赤富士など、三十八度はやや鋭角すぎますが、北斎が富士を誇張して描いたことが伝わります。太宰治の小説「富嶽百景」も連想させます。「富嶽百景」では、同時代の浮世絵師広重を登場させ「広重の富士は八十五度」と語っています。
これに対して荒井さんは、やはり北斎と同時代の伊能忠敬が、日本全国の測量を重ね、「大日本沿海輿地全図」を完成させたことを語ります。その姿に共感し、伊能忠敬は、二百年余りを経た今も測量をしていると、問いの瞬間に対して、永遠に近い長い時間を示し、返しています。浮世絵師の描いた一瞬の富士の角度と、全国を行脚した伊能忠敬の測量が今も続いているという時間との対比は鮮やかです。
《 喜びの声 》
▷荒井千代子(あらい ちよこ)さんは「文部科学大臣賞内定との通知を受け、あまりにも驚いて思考停止状態でした。今は緊張感が高まっています」と率直に感想を述べる。「問いの片歌の中の『北斎』『富士山』『角度』をキーワードに考えを巡らせていたときに、ふと測量の父と呼ばれる江戸時代の人物『伊能忠敬』が浮かびました。家業を引退し、悠々自適なご隠居の年齢だったはずです。その熱い想いは彼の死後も燃え、今も測量を続けているのではと想像しました」と答えの片歌を詠んだ。「酒折連歌は問いに対して答えるという形式なので、空想が広がりとても楽しいのです。現在コロナウイルスが世界中に禍を招いています。外出や人との交流もままならず、閉塞感が社会を覆っています。しかし世相に煩わされることなく出来ることがあります。言葉を使った創作活動もその一つです。紙とペン、時間さえあれば何時でも何処でも活動は可能です。創作中は浮世の憂さを忘れているので落ち込むこともなく、思考の切り替えで日々を過ごせるのです。外出は出来なくとも想像で無限の世界に行けます。この時代にこのような楽しみを持っていて良かったと思いました。これからも自分のペースで短詩型を詠んでいきたいと思います」とメッセージを寄せた。
●山梨県知事賞 武井大山さん(15歳 香川県 高松市立桜町中学校3年)
【問いの片歌】 これだけは手放さないよあきらめないよ
【答えの片歌】 放したら地獄戻りのこの蜘蛛の
《 選 評 》
▶︎今野寿美(こんの すみ)先生
問いの片歌から、強い志というより必死の意地を読み取り、「蜘蛛の糸」の犍陀多に変身してみせた武井大山さん。芥川龍之介のこの作品は、よく読まれ知られて主題もわかりやすく、「走れメロス」と同様、俳句や短歌の応募作に生かしやすい短編といえるかもしれません。ただ、お釈迦様を失望させた人間のさもしい欲の深さはさておき、武井さんが描いたのは救われたい一心のその部分であり、場面なんですね。だからこそ問いの片歌の答えとしてぴったりかなっているわけですが、そこで感心したのが「この蜘蛛の糸」と「この」を添え、物語を含み込みつつ七音で完結させたところです。中学三年生の手際として大いに唸らせるものでした。
《喜びの声》
▷武井大山(たけい だいせん)さんは「受賞を知ったときは『まさか自分が』と驚いています。中学校の国語の先生の提案で、授業中に1人1人応募しました。この機会を作って下さった先生や関係者の方々に感謝の思いでいっぱいです」と述べる。「色々な問いの歌があり、一番上手にひらめいたなと思ったのが『手放さない』という言葉と『蜘蛛の糸』の世界観が繋がったことでした。自分の経験よりもよく知られている文学作品の方が分かりやすく整った情景が詠めるのではないかと思いこの歌が思い浮かびました。僕が『これだけは手放さない』という言葉を見たときに頭に浮かんだのは『命綱』という言葉でした。自分の運命がかかっている「これだけは」と思ってしまう命綱は、まさに芥川龍之介の『蜘蛛の糸』に出てくる、お釈迦様が極楽から地獄へと垂らした糸にぴったりだと思いました。また、『これだけは』という言葉は『蜘蛛の糸』に出てくる犍陀多の必死さをよく表すことができると思い、その情景を片歌に詠みました。今回の受賞で詩歌の方向にも興味が湧きました。今回の受賞を機に文学的な面での創作活動に積極的に取り組みたいです」とメッセージを寄せた。
●山梨県教育委員会教育長賞 大沢美羽さん(18歳 山梨県立北杜高等学校3年)
【問いの片歌】 これだけは手放さないよあきらめないよ
【答えの片歌】 おげんきでそれでもわたし月へ帰るわ
《 選 評 》
▶︎三枝昻之(さいぐさ たかゆき)先生
問いの片歌を投げかける作者はさまざまな答えを想定するのですが、この答えは私の想定を超えたプランでした。あきらめない〈私〉ではなく、その熱意を受け止めた人の反応を通して、何をあきらめないのか、その中味を示しているからです。それで手放したくないのは君への愛でしょう。その熱意は十二分に伝わってくるけれども、応えることはできない。そこでどう断るか。なんとかぐや姫になって月に帰らねばならないから。『竹取物語』を借用したところが楽しい。どんなに熱心に求めても、相手がかぐや姫ならば、これはもうあきらめるほかないですね。かろやかな物語に仕立てたセンスに脱帽です。
《 喜びの声 》
▷大沢美羽(おおさわ みう)さんは受賞を知って「自分の作品が受賞すると思っていなかったので、とてもうれしかったです」と喜びを述べる。「一生懸命、考えてよかったと思いました」と努力が報われた。応募の動機は「学校の授業で酒折連歌を作る機会があったからです。以前、授業でかぐや姫の物語を学習したことを思い出し、問いの片歌の『これだけは手放さないよあきらめないよ』におじいさんとおばあさんの気持ちが合致すると思い、この片歌が思い浮かびました」と振り返る。「誰がきいても、同じような想像ができる作品にしたいと思い、子供から大人まで親しみのある『かぐや姫』をイメージして創作しました。月に帰ってほしくないおじいさん、おばあさんとそれでも月へ帰ると決心したかぐや姫をイメージしました」と創作意図を端的に述べる。「高校を卒業したら文学と関わる機会が減ってしまうと思うので自分から積極的に関わっていこうと思いました。これからも酒折連歌はもちろん、他の文学の創作活動も続けていきたいと思います」とメッセージを寄せた。
●甲府市長賞 高橋亨さん(64歳 青森県)
【問いの片歌】 歩く意志なくても進む朝の雑踏
【答えの片歌】 先頭を歩くのは誰誰も知らない
《 選 評 》
▶︎宇多喜代子(うだ きよこ)先生
都市のラッシュアワー時、勤務先や学校へ向かう人の脚は、まるで意志を失ったゼンマイ仕掛けの機械のように前進してゆきます。進みながら、自分がこの列の帯のどこにいるのかを知りたくても見当がつかないのです。車の渋滞に巻き込まれたときと同じです。でも、どこかに「先頭」はあるはず。それを確かめるすべもなく、ただ運命のごとく前の人の背を見て歩きます。答えの片歌にはそんなイライラの変じた諦めが「誰も知らない」という呟きになりました。この突き放したような最後の七音が、個々の意志の見えない「朝の雑踏」にぴったりです。
《 喜びの声 》
▷高橋亨(たかはし とおる)さんは「嬉しい気持ちがありましたが、何故その句が選ばれたのかと訝る気持ちになりました。二年前、酒折連歌の存在を初めて知り、一句が特選に選ばれ、それ以来すっかりはまってしまいました。ただ、選ばれた句の良さが(今回もそうですが)自分自身あまりよく理解できておらず、それが酒折連歌の面白さなのかと思っています」と魅力の要因を述べる。「問いの片歌から思い浮かんだのは、駅の改札口から次々に吐き出されるように出てくる灰色の服を着たサラリーマンの列。そこから次に、チャップリンやキートンの映画に出てくる群衆の映像。思考することを放棄した人たちが無表情で歩いていく。そんな人たちにこっちに進めと最初に言った者が必ずいた筈。そして、それがどこの誰かは誰も気にしない」という情景を詠んだ。「何かを作り出すことは単純に楽しいことで、他からの評価はどうであれ、自分で上手くできた気がした時は、それだけでわくわくします。賞に選ばれるのは勿論モチベーションを高めてくれますが、それはあくまでもおまけのご褒美だと思い、気楽に楽しみながら創作を続けていきたいと思っています」とメッセージを寄せた。
◾️アルテア部門受賞者◾️
●大賞 文部科学大臣賞 橋爪杏奈さん(12歳 静岡市立蒲原中学校)
【問いの片歌】 はればれと一円玉は一グラムです
【答えの片歌】 恋の歌軽すぎるから心が揺れる
《 選 評 》
▶︎もりまりこ(もり まりこ)先生
問いかけの目で見て確認できる物理的な重さに対して、誰にも量ることのできない心理的な感情のスケールで答えたところに、心惹かれました。恋の歌を聞いた時の詞の軽さなのか、軽快なリズムに対してなのかはわからないのですが、聞いた瞬間の心の揺れが手に取るように伝わってくる素敵な作品です。問いから飛躍した辿り着いた風景が、まったく知らない世界ではなくて誰しも感じたことのある景色であること。今というかけがえのない時間を言葉に託せることそれこそがアルテア部門の輝きなのだと、感じずにはいられない作品でした。
《 喜びの声 》
▷橋爪杏奈(はしづめ あんな)さんは「酒折連歌賞には応募者が多いと聞いていたので、自分の作品が選ばれたと聞いて、鳥肌が立つほど驚きました」と感動した。酒折連歌は「国語の授業の創作の一環として初めて挑戦しました。授業中、短歌・俳句・川柳で定型に親しんだ後だったので、少し大人っぽい内容にチャレンジしました。五・七・七と指折り数えて言葉を探し初めて挑戦しました」と振り返る。普段は「J-POPを聴くのが好きです。『あいみょん』の曲をよく聴きます。その中には、恋愛を明るく歌っている曲があり、この問いの片歌のように、晴れ晴れとした幸せな内容の曲が思い浮かび、片歌の一円玉の『軽やかさ』や『すっきりした』印象に曲のイメージが重なりました」と創作の切っ掛けを述べる。この問いの片歌に「それとは対照的に私の場合は片思いで好きなのに素直になれない自分がいて毎日、感情が揺れて動いています。相手の言動の一つ一つに心を揺さぶられます。『恋をするって、切ない。』そんな気持ちが答えの片歌になりました」と振り返る。「酒折連歌の場合は、問いの片歌5つのどれもが美しい表現なので、イメージが広がり楽しく答えの片歌を詠むことができます。来年は、どんな問いの片歌に出会えるか楽しみです」とメッセージを寄せた。
▶︎なお、コロナ禍の中、第二十二回酒折連歌賞の表彰は次の通り原則郵送を持って授与する。また、一般部門の大賞と、小・中・高校生の作品を対象としたアルテア部門には、文部科学大臣賞と山梨日日新聞社賞・読売新聞社賞・朝日新聞社賞・産経新聞社賞・毎日新聞社賞・山梨新報社賞・山梨放送賞・テレビ山梨賞の賞状と副賞が授与さる。山梨県知事賞・山梨県教育委員会教育長賞・甲府市長賞には賞状と副賞が授与される。
◾️実行委員長インタビュー◾️
廣瀬孝嘉実行委員長は「『酒折連歌賞』も回を重ねて二十二回となりました。コロナ禍の中、表彰式は中止を余儀なくされましたが、今回も嬉しいことに8歳から101歳までの幅広い年齢層から4万句を超える作品が寄せられました」と頭を下げる。「応募者の割合は10代が7割近くを占めていますが、これは学校からの団体応募が好調だからで、先生方の熱心なご指導に心から感謝しております。表現活動の一環として『酒折連歌』を採り上げ、特に今回はステイホームが奨励される日常生活の中で、家庭での学習課題として取り組まれた学校が多かったと伺っております」と。「担当の先生からは、『片歌に付けるというのは、相手からのメッセージをうまくキャッチして投げ返すこと、つまり相手を想定するという点で極めて人間的な創作だと思います。』『生徒たちも、このような機会をいただき、改めて作品を考える楽しさを感じることができたようです。』と、お便りをいただきました」また、「『酒折連歌賞』への応募を楽しみにされている60代から80代の方々の作品も増加傾向にあり、大変心強く思っております」と謝意を表す。「『酒折連歌賞』は、『問いの片歌』を提示して『答えの片歌』を募集する、全国に例を見ない文学賞となっています。この二人唱和の問答形式の文芸が、つながりを求める人々の共感を誘うものであるとするならば、この上ない喜びであります。こうした言葉遊びの裾野をさらに広げていきたいと願っています」とさらなる発展を誓った。
文(H.K) 、写真(本人及びアートボックス・シーデザイン提供) 2021.2.1
