●第二十六回酒折連歌賞入賞百選発表
~一般部門:大賞・文部科学大臣賞に金子幸男さん~
~アルテア:大賞・文部科学大臣賞に鈴木優依乃さん~
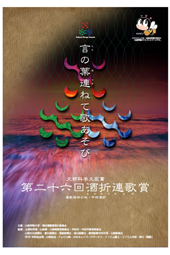 山梨学院大学・酒折連歌賞実行委員会は第二十六回酒折連歌賞の入賞百選を2月1日に発表した。今回は国内外から33,645句の応募があり、選考の結果、全応募作品を対象とした一般部門大賞・文部科学大臣賞には北海道の金子幸男さんの作品が選ばれた。金子さんは「満天の星を巡らせ指揮棒止まる」の問いに「振り向いてベートーヴェンは喝采を知る」と答えた。また、小中高校生の作品を対象としたアルテア部門大賞・文部科学大臣賞には埼玉県立越谷北高校2年の鈴木優依乃さんの作品が選ばれた。鈴木さんは「とけてゆく空のかなたに青い風船」の問いに「かなしさを込めて折られたひこうきが追う」と答えた。このほか、一般部門の山梨県知事賞には山梨学院高校1年の片桐帆乃美さん、山梨県教育委員会教育長賞には山梨県の小倉正一さん、甲府市長賞には山梨県の内藤春美さんの作品が選ばれた。表彰式は上位入賞者が出席し、2月15日に山梨学院大学で開催される。
山梨学院大学・酒折連歌賞実行委員会は第二十六回酒折連歌賞の入賞百選を2月1日に発表した。今回は国内外から33,645句の応募があり、選考の結果、全応募作品を対象とした一般部門大賞・文部科学大臣賞には北海道の金子幸男さんの作品が選ばれた。金子さんは「満天の星を巡らせ指揮棒止まる」の問いに「振り向いてベートーヴェンは喝采を知る」と答えた。また、小中高校生の作品を対象としたアルテア部門大賞・文部科学大臣賞には埼玉県立越谷北高校2年の鈴木優依乃さんの作品が選ばれた。鈴木さんは「とけてゆく空のかなたに青い風船」の問いに「かなしさを込めて折られたひこうきが追う」と答えた。このほか、一般部門の山梨県知事賞には山梨学院高校1年の片桐帆乃美さん、山梨県教育委員会教育長賞には山梨県の小倉正一さん、甲府市長賞には山梨県の内藤春美さんの作品が選ばれた。表彰式は上位入賞者が出席し、2月15日に山梨学院大学で開催される。
酒折連歌賞は、山梨学院大学と酒折連歌賞実行委員会が、大学が所在する甲府市酒折にある“酒折宮”が連歌発祥の地とされていることから、連歌への関心と創作意欲を多くの人に持ってもらおうと1998年に創設。酒折連歌は「古事記」に登場する倭建命(ヤマトタケル)と御火焚の老人との問答を踏まえ、五・七・七の「問いの片歌」に対し、「答えの片歌」を五・七・七で返す問答形式となっている。俳句や短歌などと違い、作歌上の約束事は五・七・七で返すことのみ。作者の自由な感性で答えの片歌を創作できるため、老若男女を問わず詠むことができる歌遊び。今回は国内外から33,645句の応募があり、12歳から94歳が作品を寄せ、上位5作品には以下の作品が選ばれた。
■一般部門
大賞・文部科学大臣賞 金子幸男さん(北海道)
【問いの片歌】満天の星を巡らせ指揮棒止まる
【答えの片歌】振り向いてベートーヴェンは喝采を知る
選評(西村和子先生)
演奏が終わった瞬間の静寂を、聴力を失ったベートーヴェンに重ねて、みずから指揮をとった初演の喝采を、振り向いて初めて知った感動として描き出した劇的な作品です。宇宙の星の巡りも、時間も止まったような瞬間から、聴衆の拍手喝さいの様子への転換が手に取るように見えてきます。
問答歌の問いかけと答の飛躍によって、一気に世界が広がる快感を味わうことができました。わずかな言葉で、これほど壮大なドラマが描き出せることにも感動しました。
金子さんは答えの片歌の創作背景について「答えの片歌に思いあぐねていた時は秋だった。北海道の澄んだ夜空は、手を伸ばせば届きそうな満天の星空になる。夜もすがら、星空に五線譜をひき宮沢賢治の(星めぐりの歌)に音符のかわりに星々を並べ鉛筆を指揮棒代わりにして、空が白むまで楽しんだ。やがて、東の空から希望に満ちた太陽が昇り、ささやかな一日が始まると思うとなぜか感動した。そして答えの片歌のイメージが湧いたのです」と回顧した。
山梨県知事賞 片桐帆乃美さん(山梨学院高校1年)
【問いの片歌】笑わないで答えてほしい本当のこと
【答えの片歌】モナリザの目の奥にある黒の意味とは
選評(井上康明先生)
問いの片歌は、笑っている人に真実を語って欲しいと呼びかけます。それに対して答えの片歌は、モナリザの目の奥にある瞳の色の意味とは何かと、語り出そうとします。答えを直接言わずに、語り出す姿勢を示して、余韻を残し、さまざまなことを想像させます。ふくよかなモナリザの謎めいた表情についてはモデル、背景、視線など多くの謎解きがされ、特に瞳には、レオナルド・ダ・ヴィンチのイニシャルが書かれているともされます。その黒い瞳は、深く神秘的で微かなほほ笑みを湛え、モナリザの喜びとも悲しみともつかない豊かな心情を表わしています。この答えの片歌は、瞳の黒の意味を語り始め、美しく微笑むモナリザの謎へ引き込むかのようです。
片桐さんはこの片歌について「『笑わないで答えてほしい本当のこと』という句を見た時に母がルーブル美術館に行き、モナリザの絵を見た時の、モナリザが目の前にいて、引き込まれる感じがしたという話を思い出しました。私自身も中学校の美術でレオナルド・ダ・ヴィンチについて学び、代表作であるモナリザに興味を持っていました。この問いの片歌を見た時に、モナリザと私が対峙している感じがしました。そんな私の中のモナリザで印象的だったのはもちろん口元の微笑みもですが、どこまでも落ちついていて、すんでいるようでかつミステリアスなモナリザの瞳でした。その目の奥に引き込まれていく感じがしました」とコメントを寄せた。
山梨県教育委員会教育長賞 小倉正一さん(山梨県)
【問いの片歌】大丈夫 霊峰富士の声が聞こえる
【答えの片歌】新学期教室の窓まず開けてみる
選評(三枝昂之先生)
問いの片歌を投げかける作者はさまざまな答を想定します。今回は「富士はあなたをどんなふうに励ましているのですか」と問いかけています。それに応じたさまざまな楽しい答えが寄せられましたが、小倉さんは新学期という期待と不安の入り交じる、誰もが経験したことのある場面を選んだ点にまず目がとまりました。そして、教室に入ってまず選んだ行為が窓を開ける。このプランに惹かれました。問いの片歌とセットにすると、窓を開けて目に入ってきたのが富士です。その姿正しい富士、そして周囲の風景より抜きん出た高さ。おのずから「大丈夫」という声が聞こえたはずです。問いと答えの自然な呼応が決め手となりました。しかも新学期とい学校現場、教育長賞にふさわしい問答ともなりました。
小倉さんは作歌を通じ「日本人なら、誰しも『霊峰富士』から勇気をもらい、励ましを受けているのではないでしょうか。誰がどんな場面で富士山の『大丈夫』の声を聞いているのか。酒折連歌の魅力は、一つの問いの片歌から、百人百様の答えが返ってくることにあります。私は今回、高校一年生の目線で『新学期教室の窓まず開けてみる』と付けましたが、『手を膝に試験開始を待つ五分間』『単語帳片手に急ぐ駅までの道』なども高校生をイメージして作りました。常に心がけているのは、問いの片歌が呼応し、映画の一場面、ドラマのワンシーンのように鮮やかに映像が立ち上がってくるようにすることです」と思いを語った。
甲府市長賞 内藤春美さん(山梨県)
【問いの片歌】イヤホンをはずして月の光を浴びる
【答えの片歌】ローマでもパリでもなくてここに生まれた
選評(大森静佳先生)
最近、電車のなかや街などではイヤホンを装着している人が多いですよね。私もそのひとりですが、イヤホンをはずしたときは現実世界が一瞬揺らぐような独特の感覚があります。たとえば、太古の時代からずっと空にある月の光はどう受け止められるか。答えの片歌は思いがけないのびやかさで「ここ」、すなわち日本の地で月を仰ぐ感慨を伝えてくれます。永遠の都ローマでも花の都パリでもなく、古来より月を愛してきた島国日本の片隅に生まれて来た。「ここに生まれた」という口調に、運命の不思議を噛みしめるほのぼのとした魅力があります。
内藤さんは作歌の過程について「この句を見た時にゴッホの夜のカフェテラスの絵が思い浮かびましたが、次に浮かんだのは、近くの土手の桜並木やぶどう畑やベランダから見える、四季折々の富士でした。私は、ここに生まれたんだなと思いました」とコメントした。
■アルテア部門
大賞・文部科学大臣賞 鈴木優依乃さん(埼玉県立越谷北高校2年)
【問いの片歌】とけてゆく空のかなたに青い風船
【答えの片歌】かなしさを込めて折られたひこうきが追う
選評(もりまりこ先生)
問いの片歌、「とけてゆく空のかなたに青い風船」に答えて頂いた作品です。風船が誰かの手を離れてぽつんと空に向かって舞いあがるさまはどこか物悲しいものがあると常々思っていたのですが。そんな思いに呼応したような作品に出会えました。かなしみの青い風船の尻尾を追いかけるかのように、かなしみを込めて折られた紙飛行機が追う。その情景は一度目に焼き付いたら消えてくれない情景をもって迫るものがありました。同じかなしみを共有しながら片歌の中で互いに唱和しつつ互いに寄り添っている心強い作品です。読む人々の心に触れてくれると嬉しく思います。
受賞した鈴木さんは「問いの片歌の『青い風船』からブルーな気持ちや悲しいという感情が浮かび、風船が飛ばされてしまい悲しく思う誰かというイメージが思いつきました。悲しさをそのままにしておくのではなく、風船に向けて紙飛行機を飛ばすような前向きな気持ちが伝わってほしいという思いで創作しました」と創作時の思いを明かした。
第二十六回酒折連歌賞の入賞百選や総評などは酒折連歌賞ホームページで公開されている。上位入賞者が出席して行われる表彰式は2月15日に山梨学院大学で行われ、上位入賞者に賞状や副賞などが授与される。
文(R.K)、写真:各受賞者提供 2025.2.1
