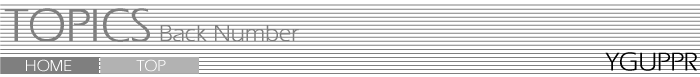
法律時報8月号「適正手続とオウム裁判」掲載
〜 オウム裁判での司法の無力を語る 〜
 日本評論社発行の法律時報8月号(7月27日発売)特別企画に、五十嵐二葉山梨学院大学大学院教授の『オウム裁判と現代社会 〜適正手続とオウム裁判〜』が掲載される。五十嵐教授は2004年2月27日オウム教祖の松本(麻原)被告の一審判決について「『なぜ事件が起きたのか全くわからないまま死刑だけ決まり、7年9ヵ月と膨大な国費を使った裁判に失望感をもった』という世論を紹介し、『何もわからなかった』感は、どこからくるのかを分析した」という。「まず、犯罪報道による先取りにより、判決文によって事実摘示されている事実を、私たちはすでよく知っているとして、司法が国民に示したものは、検察の主張(冒頭陳述)そのままで、しかも国民感情のままの死刑判決をするために、手続きを曲げて、形の上の儀式だけを執り行った」と司法の無力を語る。また世論は「真相の究明は客観的な事実が証拠によって立証されるという以上に、被告人が自らの言葉で事件を語り、反省と謝罪の言葉を語ることを求めるが、本件では裁判が長期化したのにも拘らず被告人に喋らせることと謝罪させる事をしなかったことが指弾を浴びている」という。そうした世論の中「1995年3月の地下鉄サリン事件ではじまったオウム犯罪の司法過程は、捜査から起訴、公判と、その全ての段階で履践されてきた刑事手続上の保障レベルすら一気に破壊したといえる」と語り、「そうした状況下での弁護団の弁護活動はあれでよかったのか」と疑問を投げかける。法律時報論稿は、1.司法の無力 ①事実認定、②裁判は懺悔と謝罪の場、2.オウム事件による刑事手続の歪曲、3.適正手続破壊と弁護活動について書き下ろしている。
日本評論社発行の法律時報8月号(7月27日発売)特別企画に、五十嵐二葉山梨学院大学大学院教授の『オウム裁判と現代社会 〜適正手続とオウム裁判〜』が掲載される。五十嵐教授は2004年2月27日オウム教祖の松本(麻原)被告の一審判決について「『なぜ事件が起きたのか全くわからないまま死刑だけ決まり、7年9ヵ月と膨大な国費を使った裁判に失望感をもった』という世論を紹介し、『何もわからなかった』感は、どこからくるのかを分析した」という。「まず、犯罪報道による先取りにより、判決文によって事実摘示されている事実を、私たちはすでよく知っているとして、司法が国民に示したものは、検察の主張(冒頭陳述)そのままで、しかも国民感情のままの死刑判決をするために、手続きを曲げて、形の上の儀式だけを執り行った」と司法の無力を語る。また世論は「真相の究明は客観的な事実が証拠によって立証されるという以上に、被告人が自らの言葉で事件を語り、反省と謝罪の言葉を語ることを求めるが、本件では裁判が長期化したのにも拘らず被告人に喋らせることと謝罪させる事をしなかったことが指弾を浴びている」という。そうした世論の中「1995年3月の地下鉄サリン事件ではじまったオウム犯罪の司法過程は、捜査から起訴、公判と、その全ての段階で履践されてきた刑事手続上の保障レベルすら一気に破壊したといえる」と語り、「そうした状況下での弁護団の弁護活動はあれでよかったのか」と疑問を投げかける。法律時報論稿は、1.司法の無力 ①事実認定、②裁判は懺悔と謝罪の場、2.オウム事件による刑事手続の歪曲、3.適正手続破壊と弁護活動について書き下ろしている。
■五十嵐二葉 掲載情報
「季刊 刑事弁護 『特集 刑事弁護の中の取引経験1 〜制度設計には実態解明が不可欠〜』掲載」 (7月10日発売)