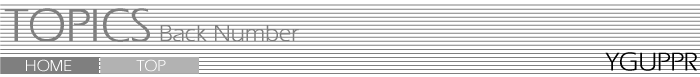
政治行政学科3年 江藤俊昭ゼミ
地方分権時代「おらんとうの憲法条例」制定で住民を喚起
 山本さんは、「今こそ、憲法94条『地方公共団体の機能』の範囲内で、住民参加を中心とした自治基本条例を制定すべきだ」と市民・議員や行政に呼びかけている。
山本さんは、「今こそ、憲法94条『地方公共団体の機能』の範囲内で、住民参加を中心とした自治基本条例を制定すべきだ」と市民・議員や行政に呼びかけている。
大学2年生のときに、日高昭夫ゼミで「地域を良くするための政策作りの取り組み」を調査研究した。「当時は広域合併が花盛りで、多くのゼミ生が市町村合併に着目していたので、他に何かないかなと実家のある静岡県の伊東市に帰り調べてみると、議員さんらが自治基本条例に取り組んでいました。議員さんらは、『地方分権の時代は、地域(住民参加)で地域のルールを立ち上げなければいけない』と、自治基本条例制定に取り組んでいました。『これだ』と思いました」と、自身が取り組む課題「小さな町での議員の試み 〜自治基本条例制定に向けて〜」が決定した瞬間だった。「結局、議員さんや参加住民の思いは通じず議会で自治基本条例は否決されました。その時は、『え、何故。地域を良くするための取り組みなのに』と、本当に落胆しました。日高ゼミで、このプロセスについて研究報告しました」と、目を伏せる。
山本さんは3年生になって、日高ゼミで学んだ伊東市の自治基本条例の取り組みのプロセスの教訓を生かして「自治基本条例制定を学びたい」と、江藤ゼミの門を叩いた。江藤ゼミは3年生18名で、そのうちの8名の賛同を得て、プロジェクトチーム「江藤ゼミ自治基本条例グループ『たくら』を結成した。
そして、「江藤先生の助言もあって、メンバーの話し合いで『自治基本条例制定を学びたい』から、『甲府市に自治基本条例制定を目指そう』」と言うことになった。
チーム名が甲州弁なのは「身近に感じて地域の人たちに関心を持ってもらいたいのが狙いで付けました。また、『たくら』は甲州弁で『仲間』という意味です。地域の人々に仲間になってもらって、共に制定を目指しましょうという意味合いもあります」と、さらに「自治基本条例文も甲州弁で作成しょうと考えています」と話す。
「地方分権時代だからこそ、住民自身が政策形成過程や執行過程に直接かかわることが重要なのです。現に、ゼミ生以外にチームに参加してもらっています。また、甲府青年会議所の町づくり特別委員会と協力して行っています」と強調する。これまでの取り組みは、「1)甲府青年会議所メンバーとの話し合いや勉強会。2)自治基本条例の意義と必要性、憲法・法律との関係性、最高規則に関する問題などの勉強。3)各地の自治基本条例調査。4)甲府市の政策条例について学習。5)フォーラムの開催。6)ホームページの作成、などです」と話す。「9月中旬に、市民と共につくる自治基本条例『おらんとうの憲法条例』の中間報告を完成させました」と、微笑む。
これからの活動は「1)条例案の作成。2)勉強会。3)ホームページやシンポジウムなどで市民に公開する。4)条例の完成。5)甲州弁、英語、中国語に訳すなど」と「甲府市に制定してもらえたら最高です」と控えめに話す。
「地方分権一括法が2000年4月に施行され5年を迎えようとしています。私たちの活動で、甲府市民や他地域の住民の方が、『自分たちの町は自分たちの手でつくる』という気概を抱いてもらえたら、本当に最高です」と、真意を覗かせた。
学生ゼミが、地方分権時代に「おらんとうの憲法条例」の提案で、住民意識を喚起していることの意義は大きい。
■「たくらホームページ