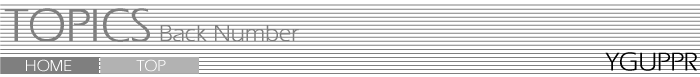
平成16年度外務省「日中知的交流事業支援事業」
〜 12/20 シンポジウム『中国 法治社会への転換』開催〜
 今年度、山梨学院大学大学院法務研究科は外務省が募集する平成16年度『日中知的交流事業支援事業』に応募し6月に採択された。山梨学院大学法学部教授 中井道夫さんは、この事務局を務めている。
今年度、山梨学院大学大学院法務研究科は外務省が募集する平成16年度『日中知的交流事業支援事業』に応募し6月に採択された。山梨学院大学法学部教授 中井道夫さんは、この事務局を務めている。
これまで山梨学院大学は、中国人事部人事科学研究院や中国社会科学研究院法学研究所、復旦大学、南開大学などと学術交流を行ってきた。そのテーマは行政改革、許認可行政、西部大開発における人材育成、医療・年金改革など。
中井さんは「現在、中国では『法治社会』に向けて法整備が急がれております。この動きをうけて山梨学院大学法科大学院では、外務省の『日中知的交流支援事業』に、テーマ『中国の法治社会構築に向けての日中共同研究』を計画し応募しました。これは、日本の経験をふまえることによって中国の法治社会構築に向けての諸課題を検討し、提言を行うことを調査研究・交流するもので、外務省に採択されました」と切り出す。
「中国が今後、開放改革の波を一層推進させるためには、1) 外国企業の進出における許認可制度の地方分権と迅速化の必要性、2) 中国の行政や社会生活全般における法整備の推進。これらの諸点は中国の近代化のために非常に大切なことであり、日本の経験が大いに参考になる分野である」と力説する。
具体的には「小野寺規夫大学院法務研究科長には、日本での司法改革と現状と方向性。上條醇法学部教授には、物権法の制定、日本の経験と中国物権法制定への方向性。小野寺忍大学院法務研究科教授には、日本における民事訴訟制度改革と中国民事訴訟の実情と将来動向。熊達雲大学院社会科学研究科教授には、中国の『独立審判』と日本の『裁判独立』。立田清士河中自治財団理事長には、日中両国における行政許認可制度の比較。私は、日本都市計画史からみた紛争処理と中国土地開発過程での法整備について調査研究する。また、中国人学者4名にも参加してもらい交流を深めます」というもの。
既に中井さんらは、「今年の9月8日から9月20日に中国の北京・威海・青島・大連・瀋陽にシンポジウムの開催と現地調査研究・交流で訪れました。例えば蘇州の町のいたるところに『法治社会』というスローガンが掲げられていて法治社会構築に全身全霊でとりくんでいることが窺い知れました。勿論、シンポジウムや現地調査研究・交流は盛況でした」と、着実に実績を積んでいる。
今度は、12月20日東京の日中友好会館地下1階大会議室でシンポジウム『中国、法治社会への転換』をテーマに第1部・第2部の構成で行う。
「第1部は『中国の司法改革、民法典整備』をテーマに、北京大学法学院の賀衛方教授が『中国の裁判所改革と司法独立』について、中国社会科学院法学研究所の渠涛教授が『中国の民法典編纂』について、山梨学院大学法科大学院の小野寺規夫研究科長が『日本における司法制度改革と法科大学院』について報告を行います。コメンテーターは一橋大学法科大学院の西村幸次郎教授と山梨学院大学大学院法務研究科の辻千晶教授が務めます」。
「第2部は『中国の法に基づく行政』をテーマに、中国国家行政学院 應松年法学部部長が「中国の法に基づく行政」について、中国政法大学法学院 馬懐徳院長が「中国の都市開発の法整備」について、一橋大学、筑波大学の南博方名誉教授が「日本行政法からみた中国の行政法」について報告を行い、コメンテーターに東京大学の塩野宏名誉教授、山梨学院大学大学院法務研究科の椎名慎太郎教授が務めることになっています」。「多数の皆様のご参加をお待ちしています」と語った。
今まで、日中は産業での交流は盛んに行われてきたが、法制度における踏み込んだ知的交流支援事業は初めての試みとなるだけに、このプロジェクトに期待したい。
■ 中国におけるシンポジウム アルバム
■ 中国現地調査研究・交流 アルバム